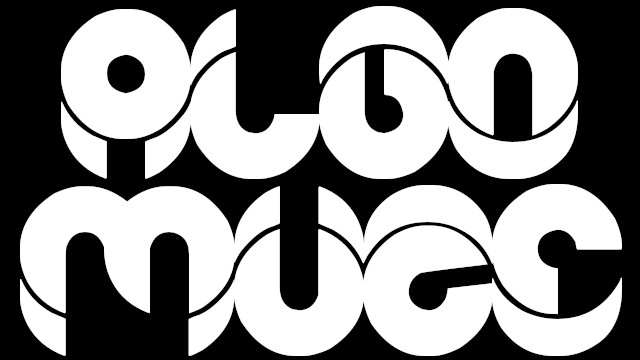第2章 ソナタ形式の文化とその崩壊
ではそれぞれの構造にどのような例があるか、西洋クラシック音楽から探っていく。
まず内側の構造については二つの種類がある。それは「要素を繰り返す構造」と「要素の集合体を繰り返す構造」である。前者の例としてはカノン、フーガ、インベンションなど、後者の例としてはロンド、変奏曲などが挙げられる。
外側の構造の例としては、フォリア、ガヴォット、メヌエットなどが挙げられる。これらはいずれも内側の構造を持っているが(フォリア:変奏曲、ガヴォット:二部形式、メヌエット:複合三部形式)、同時に舞曲であるため、その舞曲の様式が要求するテンポや旋律、ハーモニーなどの制限がある。それらを遵守するということが、すなわち外側の構造を生み出すのである。つまり、同じく様式を遵守した他の作品群と自分の作品が相対化されるということである。したがって、外側の構造とは「慣習的構造」「流行的構造」とも言い換えることができる。
それを踏まえて、18世紀後半から20世紀初頭まで流行した、特に交響曲や室内楽では作曲の前提条件にすらなっていた「ソナタ形式」について分析していく。なぜこれだけの長い期間、多くの作曲家にソナタ形式が支持され続けてきたのか。音楽学では既にそれなりの説明が与えられているのだろうと思うが、ここでは学術的に正当かどうかではなく、あくまで創作者としての視点から見た歴史的変遷について、私個人の意見を述べていく。本論の意義は、学術的な正確さではなく、芸術的観点からの説得力があるかどうかに懸かっていると私は考えるからである。
私の考える重要なポイントは以下の二つである。
①ソナタ形式は二種類の「内側の構造」、すなわち要素の繰り返しによる構造と、要素の集合体の繰り返しによる構造によって成立し、その後「外側の構造」としての地位を確固たるものにしたこと
②ソナタ形式が獲得した「外側の構造」は、「作曲者の創造の指針」であると同時に「鑑賞者の構造把握の指針」であり、それによるコミュニケーションが生まれたこと
ソナタ形式がどのような内側の構造を持っているか。これについてはソナタ形式についての教科書通りの知識があれば十分なので、ここでは省略する。重要なのは、ある時期以降、少なくともベートーヴェンとそれ以降の作曲家にとっては、その学習期において既にソナタ形式は外側の構造として存在していたということである。無論、ベートーヴェンの時代には「ソナタ形式」という単語そのものは存在していなかったが、彼に与えられたモデルの数々が「選択の連続」によって展開されていることに、作曲家は必然的に気が付くのである。
・主題のどのモチーフを使って経過部を作るか、同時にどう転調を仕掛けるか
・第1主題と第2主題をどのように対比させるか
・提示部をどう終結させれば繰り返しの第1主題が面白く聴こえるか
・展開部の冒頭をどのように始めるか
・展開部の規模をどうするか、またそれに相応しい動機労作はどのようなものか
・再現部の冒頭を印象的にすべきかどうか。また、そのためには展開部をどう終結させればよいか。
・提示部では転調操作された経過部を、再現部ではどのように対比させるか……等々。
これらの研究を経て、作曲家はまず、モデルと遜色ないような「外側の構造」の獲得を目指す。やがて技術を修練させていくと、クリシェを避けようとして、外側の構造の「従属と逸脱」のバランスを取るようになる。その際に生じる「期待と裏切り」こそが、すなわち作曲者と鑑賞者とのコミュニケーションとなるわけである。作曲者にとっての選択の連続はそのまま「鑑賞者にとっての評価判断」となるのであり、鑑賞者は不可逆的な音楽進行の中にあっても、「作品理解のための構造把握」と「芸術的な価値判断」の両方を同時に行うことができる。この作曲家と聴衆の関係性が「クラシック音楽の黄金の時代」を形成した。
メヌエットやスケルツォなど外側の構造を持つ形式は他にも存在していたが、いずれもソナタ形式ほどに「逸脱」を促す構造的特徴を持っていなかった。であるからこそ、シンフォニーの4楽章の中で、複雑化しやすいソナタ形式と複雑化しにくい緩徐楽章やスケルツォでバランスを取っていたのである。
フーガにも外側の構造は存在するが、ソナタ形式ほどの強固なものには至らなかった。それはフーガの本質が即興だからである。現代でもフーガの即興演奏はオルガニストにとっての必須の技能である。ポリフォニーの絶え間ない進行の中での主題の配置と色彩の変化をその場その場で紡いでいくフーガは、したがって全体の構造から逆算して作られるものではない。また、作品規模にも自ずと限界が生まれ、一つのフーガが10分を超える例はほとんどない。バッハの無伴奏バイオリンソナタのフーガやベートーヴェンの大フーガなど、10分を超える傑作フーガは確かに存在するが、それらはいずれもフーガではない部分を挟み込むことで作品の巨大化を図っている。その「フーガと非フーガの組み合わせ」が強固な外側の構造になるという可能性はあったかもしれない。しかし歴史上はそうはならなかった。これはまったく個人的な推察だが、フーガの最大の魅力はその導入部である。それまでハーモニーを伴って進行していた音楽の中で突然単旋律の特徴的なメロディーが始まった瞬間、聴衆はフーガの始まりを予感する。その期待通りにフーガが進行し、作曲家の技巧を存分に披露した後、「1、2分間程度のちょうどよい長さ」で終結もしくは他の楽想へ繋げる、というのがフーガに与えられた役割だった。フーガの持つ徹底した内側の構造は、それ自体を外側の構造として研究・発展させるよりも、他の構造へと従属する形で組み込む方が美学的に優れた作品を生み出しやすい、というのが歴史上の作曲家たちの判断だったのではないかと私は考える。
ソナタ形式が崩壊する最初の予兆はおそらく展開部とコーダの拡大にあったと私は考える。偉大な作曲家たちによって開拓されていった和声法やオーケストレーションが生み出す新たなポエジー(音楽的詩情・音楽的霊感)は非常に強力で、その結果作曲家と聴衆の間で交わされる「遊戯的コミュニケーション」よりもポエジーの追求の方が優先されていった。したがってソナタ形式の中でも制約の少ない展開部とコーダがポエジーの発露の場として拡大していくのは自然な道理である。そうしてかつて「従属と逸脱」のバランスの中で作られていたソナタ形式が、従属すべき部分をどんどん排除していった。聴衆は作曲家による「選択」を聞き取るのではなく、神のごとく創造された音楽的世界のポエジーに浸るだけのコミュニケーションへと変化していった。
【シェーンベルクの夢】
ソナタ形式の外側の構造が崩れるに従って、必然的に内側の構造も崩れていく。そんな中にあってシェーンベルク(※1874年生まれのドイツの作曲家。作品の良し悪し、好き嫌いはともかく、音楽史上で非常に重要な作曲家。現代音楽の始祖のような存在)という作曲家は何をしようとしたのか。「冒頭で提示された主要動機の中にその後の展開が全て内包されている作曲」という理念を持っていた彼は、その実現のために「発展的変奏」という手段をとった。すなわち主要動機をそのままの形ではなく、少しずつ変形させながらそれを段階的に散りばめて作曲を行った。主要動機という種から萌芽した展開が発展的変奏という枝分かれを繰り返し、最終的に作品という樹木になるというわけだ。一般的にこうした作品構造を「有機的」と形容するが、私に言わせればそれは幻想である。ここで第1章の冒頭をもう一度繰り返す。
「構造とは繰り返しの認識であって、繰り返しそのものではない」
変形された動機はもはや変奏ではなく、新たな動機かつ重要ではない動機としか認知されない。この手法は作曲を進めていく上では大いに手助けとなるかもしれないが、それ以上の価値はない。彼がやっているのは「変奏曲とは認識されない変奏曲」と同じである。その結果一つの作品が出来上がるのは確かだが、それが変奏曲の構造を持っているとは呼べないのである。
そもそも古典時代のソナタ形式の内側の構造を認知することさえ本来は困難なことである。ではなぜそれが確かな構造として存在していたのかと言えば、それは外側の構造のおかげである。つまり、一人の作曲家ではなく世代を超えた多数の作曲家が共通の理念を持ち、互いの仕事を観察し合い実践を繰り返すことで、二部形式という種からソナタ形式を萌芽させていったのである。そうしてソナタ形式の外側の構造が少しずつ強固になっていくにつれ、それを頼りに内側の構造も強固かつ複雑にすることが可能となったのだ。
したがって、シェーンベルクの発展的変奏という手法が真に「有機的」になるには、彼一人がその手法で作曲するだけでは不可能なのである。彼の二人の弟子(※ベルクとウェーベルンのこと)だけでもまったく不十分で、もっと多くの作曲家がその理念に共鳴し、実践と観察を繰り返しながら外側の構造を少しずつ作り上げていくしか道はない。つまり、「作曲家しか知らない秘密の鍵——認識が難しい作曲技法」を「内側の構造」へと変貌させるには、その文化集団(作曲家、演奏家、聴衆、批評家など)をいわば教育し、数多くのモデル学習を経て「外側の構造」の獲得を経ることが絶対条件なのである。そうすれば、認知が極めて難しい発展的変奏が内側の構造を獲得する未来もあったかもしれない。実際はシェーンベルクが「構造とは何か」という根本を理解していなかったために彼の目論見は失敗に終わったが、失敗こそが歴史を豊かにする最大の原動力であることを忘れてはならない。
シェーンベルクの偉大なる失敗から私が継承したものは何か。その答えは第4章で提示していくが、その前に現代音楽の現状を整理しておく必要がある。