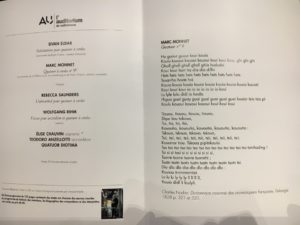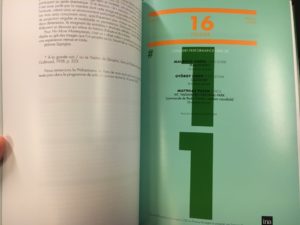2月16日、ラジオフランスで開催中のFestival Présences 2019、第5日目のコンサートへ行ってきました。
フェスティバルの概要については2日目の記事をご覧ください。
今回は記事が長いです。なんせ5つのコンサートがありましたからね。14時半から23時半までずっと現地にいました。
まずは1つ目の紹介、の前にラジオフランスの建物を紹介しておきましょう。いつも夜のコンサートのときにしか行かないのですが、昼間に来たのは初めてなので僕自身新鮮でした。
ラジオフランスはこういう円形の大きな建物です。そういえばアップルの本社もこんな形ですね。コンサートで使われるホールは主に二つ備えられています。
フェスの期間なのでリームの特集パネルが置かれていました。
さて早速一つ目のコンサートから紹介していきましょう。
Jörg Widmann (1973-) «Babylon Suite» (2014)
最初は一曲だけです。作曲者はドイツ出身、クラリネット奏者として多くのオーケストラと共演していますが、作曲もリームに教わっていたようです、優秀ですね。もともとは同名の一幕物オペラが2012年に作られたのですが、言語に頼らない表現を志向してこの組曲もその後作られました。
パロディー表現が多く使われていたのが印象的です。行進曲やダンスの定番の伴奏形にちぐはぐな旋律をのっける、割とよくある方法です。まあこれも音楽に限った話ではないですが、パロディーをやるならそれはそれできっちりやらないと中途半端になる危険が常に伴います。表現としてのパロディーで終わるのではなく、もっと作り込んでほしかったところですね。ここらへんショスタコーヴィチやストラヴィンスキーは本当に上手です。
実際の演奏中はこのようにスクリーンが設けられて、そこに古代バビロニアをモチーフにした静止画イラストを色々演出しながら投影していましたが、まあ得てしてこういうのはそれほど面白くはありません。イラストは美術学校の学生が手がけたようです。オーケストラの中にアコーディオンも紛れていて、その使い方は面白かった部分もあるのですが、全体としてはぼちぼち、という感じでした。4.5。
さて続いてはコンサートではなくイベント。
ここに思いっきりavec Rihmと書かれているので、本人が自作品について語るトークイベントだと思っていたのですが、実際は来ず、指揮者や演奏家たちがリームとの出会いを話すというものでした。がっかりだよもう。会場は窓ばりでしゃれていましたけど。
まあ特に話すこともないのですが、やはりドイツ本国ではリームはモニュメンタルな存在のようですね。そりゃそうでしょうね、今の時代にあって世界的に広く認知されている作曲家自体がかなり減ってしまいましたからね。現役の作曲家の中では最も有名な一人でしょう。
さて続いてはカルテットのコンサートです。
演奏順に作品紹介をしていきます。
1. Sivan Eldar (1985-) «Solicitations» (2019) (国内初演)
作曲者はイスラエル出身の女性で、IRCAMの元研究生。作品は「音色展覧会」の典型例で面白くなかったです。これは僕の造語ですが、要は特殊奏法で何ができるかを一覧にして並べただけのような作品のことです。オーケストラならまだしも、室内楽でこれをやると99%失敗します。2.5。
2. Marc Monnet (1947-) 『弦楽四重奏曲第9番』(2017) (世界初演)
フランスの作曲家。弦楽四重奏にソプラノを加えた作品です。プログラムの右側に書かれている呪文のようなのが歌詞ですね。先ほどの作品よりはマシですが、声の使い方がそれほど面白いわけではなく出番も少ないので、この特殊な編成にした狙いがよくわからないです。3.0。
3. Rebecca Saunders (1967-) «Unbreathed» (2017)
イギリスの女性作曲家。ようやくまともな室内楽がきたか、と一安心。ほぼ特殊奏法しか使われていないのは前2作品と変わらないのですが、音作りのレベルが全然違います。耳を使って作曲してるな、というのが伝わる感じ。中盤のリズミカルな書法が面白かったです。特にスルポン・スピッカート(駒の近くで金属的な響きを出しながら弓を跳ねさせる)で刻んでいくのが良かったですね。その後頂点まで盛り上がったあと静的なシークエンスが続くのですが、あれは蛇足だったなーと個人的には思います。頂点で終わった方が無駄がなくて「おお!」と終われて良いんですが。まあしかし面白い作品でした。6.0。
4. Wolfgang Rihm (1952-) «Fetzen» (1999-2004)
ここに来てようやくリームの登場。弦楽四重奏にアコーディオンを加えた作品です。今日の最初の作品といい、アコーディオンは現代音楽での花形になりつつありますね。作品は全部で8つに分かれていて、今回はその中から3、5、6、7、8曲目の5曲抜粋で演奏しました。
アコーディオンと弦がともに高音部を鳴らすとどっちの音なのかわからなくなるんですよね、面白い。僕は第7曲目のが一番気に入りました。アコーディオンの使い方はもっと面白い方法がありそうな気もしますが、弦は室内楽っぽい魅力が出てます。5.5。
Youtubeにこの曲の録音がありました。7曲目は18:30からです。
演奏はディオティマ弦楽四重奏団。1996年にパリ高等音楽院で結成して、現代音楽を中心に演奏しています。専門集団なだけあって、技術の高さはさすがでした。また別な機会でも聴いてみたいです。
さて聴いてる僕にも疲れが出てきました。でもここからが本番! 次はアンテルコンタンポランの演奏です。
1. Florent Caron Darras (1986-) «Milan noir» (2018) (世界初演)
今回のフェスで一番若い作曲家です。経歴を見ると日本生まれなんですね。ですが名前もそうだし見た目もまったくアジアっぽくないので、両親とも日本人ではないと思われます。
作品は指揮者なし、ピアノ付き6人の室内楽。これは良かったです。全体的にリズミカルでシークエンス的な作風ですが、構成も音もよく練られています。ピアノがほぼ単音しか使ってないのも面白いですね、ついつい音を重ねたくなってしまうのが普通ですから。
チェロが中盤で一番低い弦(C線)で強いピチカートを連続してやっていたのですが、なんと演奏中に弦が切れてしまった!!
チェロの弦がくるくるってなってるのが写真でわかるでしょう。まあチェロの、しかも一番太い弦が切れることは滅多にないのですが、あれだけのピチカートをやってたら可能性は確かにあります。作曲というのはこういうのも考慮する必要があるのです。演奏者や楽器に負荷をかけると、それに応じたリスクが当然生じます。それを含めての表現ですから、まあそこが面白いところでもあります。
いやしかしチェロは見事でした。弦が切れてからも5分くらいは曲が続いてましたが、まったく動揺を見せず、さらにG線を緩めて音を下げながら対応するという荒技まで繰り出してきました。ここらへんの対応力がさすが専門集団って感じですよね。自分が作曲者だったら演奏が終わって登壇したら真っ先にチェロに礼を言うんですがね。まあ残念ながら将来そういう機会に巡り合うことは天文学的確率で低いでしょう。
まあそんな事件があったのでついついそっちに目がいってしまいましたが、作品自体は良かったです。6.5。
2. Máté Bella (1985-) «Hesperus» (2017)(世界初演)
ハンガリーの作曲家、こちらも若いです。作品はヴィオラソロと室内楽の作品。協奏曲と銘打ってないだけあって、ソロが目立つような作りにはなってません。弦セクションのシークエンスと管セクションのシークエンスが交代しながら、その間をふわふわ漂うようなヴィオラ。それほど注目すべきポイントはなかったです。3.5。
3. Wolfgang Rihm (1952-) «No more Masterpieces» (2006-2015)
さてこれが問題の作品。一言で言えば長っげえ上に退屈。50分超の作品です。これから先何度機会が訪れたとしても最初から最後まで集中して聴くのは僕には不可能だと断言できます。僕にとってこれは「悪い意味、最悪の意味でのカオス」でしかなく、一番嫌いなタイプの一つです。終わった後でそこそこブラボーが飛んでましたが、本当に心の底からそう思ってるのなら、一体なにが良かったのか教えてもらいたい。真剣に。2.0。
これまた映像付きの作品で、ドイツの 33 1/3 Collective という映像制作集団が手がけたそうですが、まったく面白くない。でも新作でこういう類のものはいつも同じです。一度でいいから映像付きの音楽作品でまともなものを見てみたい。僕からすればネット上に転がってるものの方がはるかに見どころがあります。
もしこれが作曲の世界で名作だと認定されたとしたら、僕は喜んでこの世界から立ち去ります。これからの評価が楽しみですね。
さて長い1日もこれで最後です。今日もまたアクースモニウムです。
1. Mauricio Kagel (1931-2008) «Transición 1» (1960)
カーゲルはアルゼンチンの作曲家、ダルムシュタット組ではありませんが有名な現代作曲家の一人です。この時代の作品なので技術的な限界が当然あるのですが、それにしてももう少し工夫が欲しいところです。やはり電子音楽に特化しているフェラーリやパルメジャーニに比べると弱い。2.5。
2. György Ligeti (1923-2006) «Glissandi» (1957)
リゲティはハンガリーの作曲家で、ブーレーズ、ベリオらと同じダルムシュタット組の一人。僕がこの世代で最も好きな作曲家の一人です。器楽曲は名曲がたくさんあるのですが、電子音楽は初めて聴きました。なかなか良い感じです。カーゲルの作品と同じ年代とは思えないほど音を自在に操ってます。スピード感のある素材が多いので、アクースモニウムにも合っていますね。4.5。
3. Matthias Puech (1983-) «Mt. Hadamard National Park» (2019)(世界初演)
フランスの作曲家。30分の作品でどうなることかと心配しましたが、面白かったです。全体で5か6のパートに分かれていて、それぞれ一つか二つのシークエンスを繰り返しながら音を重ねていく構成。その作り自体は単純なのですが、シンセシスの重ね方が良くて各パートの対比もとれているので、飽きない作りになってました。しかし何よりも…
まあ最初はこんな風にミキサーを操っていました。これが普通の光景なのですが、ある瞬間に突然照明が変わったと思ったら、彼がしゃがんで何かもぞもぞ準備しています。そして、
!?
しかもなんか近づいてくる! 彼はミキサーを放置していきなり踊り始めました。なんだこれは。なんだそのイカは。この妙なユルさ、嫌いじゃないです。しかしアクースモニウムのコンサートで踊り出す作曲者は初めて見ました。二度と見ることはないでしょう。
まあなんか色々記憶がぶっ飛んでしまう事件でしたが、作品自体は良かったです、ほんとに。曲が良くなかったら許されませんからねこんな蛮行は。それをわかってるあたり、大したものです。6.0。
まあとにかく盛りだくさんの1日でした。ここまでぶっ通しで会場に居続けたのは僕一人だけでしょう。さすがに水は持って行きましたが、空腹がまったく気にならないという僕の数少ない長所が活きましたね。あー大変だった。