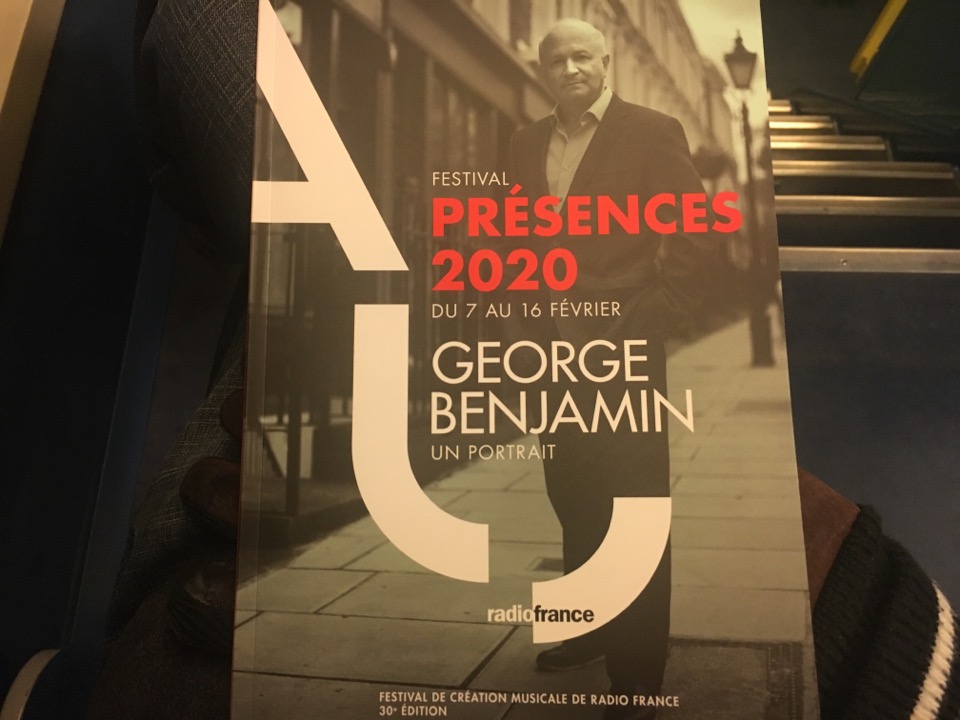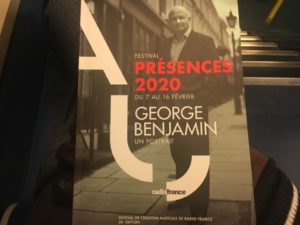今年もこの季節がやってまいりました。パリの現代音楽の祭典、Festival Présences 2020の開幕です。
去年はドイツの作曲家、リームの特集でした。そのときの様子はこちらをご覧ください。

今回でこの祭典も第30回を迎えるという記念すべき年になりました。今年の特集作曲家はジョージ・ベンジャミンです。概要は日本語版Wikipediaにあるのでご覧ください。
これが今年のプログラム(5ユーロ)です。内容盛りだくさんなんで有料なのは全然構わないんですが、これを毎回持っていかなきゃ行けないのは少し面倒です。
1960年ロンドン生まれ、ついこの間誕生日を迎え60歳になりました。ブーレーズもかくやというほどの神童ぶりで早くから実績を積み重ね、今日では現代音楽の世界で最も重要な作曲家の一人となりました。ピアノ・指揮の腕前も専門家トップレベルで、ラヴェル・メシアン・ブーレーズの系譜を引き継ぐ、まさにミュジシャン・コンプレ(完璧な音楽家、より狭義的には楽器も指揮もできる作曲家という意味)そのものというような人です。
そんな音楽の巨人、人類の至宝のような人の作品に対して、僕みたいな全く取るに足らない人間が好き勝手書いてやろうってんですから、ほんと現代は面白い時代ですね。時代の問題か?
さて、このフェスティバルのコンサートは全てフランスミュージックのHPで聴くことができます。上の方のContemporain(現代音楽)をクリックして、Festival Présences 2020を探してみてください。今回のは2時間28分の長さのものです。そう、本当にコンサートの録音が丸々上がっているんです、素晴らしいですよね。日本でもこういうことやってくれたらいいんですけどね。PCでご覧の方は下のバーでシークと音量調整ができます。
少なくとも一ヶ月くらいはアーカイブが残ると思うので、もし後からこの記事を読んだ人でも興味あれば覗いてみてください。検索窓もあるので、探しやすいはずです。
では初日のプログラムです。
今回の演奏はフランス国立管弦楽団、指揮はベンジャミン本人です。フランスミュージックのアーカイブのタイムラインも合わせて記しておくので、聴く際の参考にどうぞ。
1. Gérard Pesson (1958-): «Ravel à son âme» (2011) ※国内初演
-7mn 10s-
最初に登場したのはフランスの作曲家。大学で文学・音楽学を専攻した後、高等音楽院で作曲を学び、現在は音楽院の先生になっています。
オーケストラ作品。オーケストレーションは1920年〜40年頃のスタイルですが、音楽性はもっと時代が進んだ感じの、不思議な作品ですね。タイトルは『ラヴェル、その魂に』ですが、個人的にはラヴェルというよりストラヴィンスキーっぽい印象を受けます。
短い作品ですが、オーケストラの使い方、音響の作り方は見事なもので、さすが音楽院の先生といった感じの、お手本のような作品ですね。パルス(拍動)を打楽器などで刻むシークエンスが多いですが、そこらへんのやり方は僕好みです。5.5。
今回2階席の最前列だったんですが、写真でわかる通りここめちゃくちゃ良い席なんですよね。普通はこれくらい上の角度がついてる席だともっとステージから遠いんですが、このホールはかなり距離が近いです。ホールの大きさもちょうど良くて、超大規模オケじゃない限り、新作を聴くならフィルハーモニー・ドゥ・パリの大ホールよりずっと好きですね、こちらの方が。去年もここに来てるはずなんですけどね、何で今更こんな風に思ったのか。
2. George Benjamin: «Duet» (2008)
-18mn 8s-
いよいよご本人の作品。タイトルのデュエットというのは、ピアノとオーケストラのデュエットという意味。コンチェルトではないということですね。そしてオケの編成が少し変わっています。
バイオリンがごっそり抜けて、ヴィオラ以下の低弦群だけ残りました。席を移動することなくこのままやるのが面白いですね。
大雑把に言えば急緩急の構成で、真ん中の緩がかなり長くなっています。中音域で怪しげに動き回るピアノソロから始まって、後にオーケストラが加わる。ピアノは超絶技巧めいたものは一切なく、むしろ単音でポーンポーンと弾くのが多いくらいで、確かにコンチェルトとは全然違うスタイルです。正直ピアノソロの彼女は見ていて技術的に多少不安を覚える感じだったのですが、このスタイルなら問題はなさそうですね。
オーケストラで特殊奏法はほぼ使っていないと思いますが、それでも古臭くならず、新しい響きを模索しているのが良いですね。音の重ね方も、濁ってぶつかるような響きは一切なく、細部まで神経が行き届いているのがわかります。ただ、中盤が少し退屈だなと思う箇所がいくつかあるのと、構成的な面白さには欠けるかなという印象です。5.0。
3. Hans Abrahamsen (1952-): «Left, alone» (2015) ※国内初演
-37mn 5s-
コペンハーゲン生まれの作曲家。デンマーク王立音楽アカデミーでホルンと作曲を学んだ後、リゲティにも師事したそうです。
タイトルに付随して「左手ピアノとオーケストラのための」と書かれています。ラヴェルが1930年に『左手のためのピアノ協奏曲』を作曲して以来、多くの作曲家が同じ左手ピアノのコンチェルトを作るようになりました。僕もこれまで4つくらい聴いたことがあります。これも前の曲と同様コンチェルトとは書かれていませんが、その流れを組むような作品なのではないでしょうか。
ピアノとコントラバスの唸るような低音から始まる。こちらも前の曲と似た感じで、ピアノを単音で鳴らしたりしていますね。特殊奏法がほとんどないのも似ていますが、途中でピアノの鍵盤の裏の部分をコンコン叩いたり、ハープをスーパーボールスティックで叩いたりするような箇所はあります。最後の方でピアノが右手で楽譜を持って左手で内部奏法をする場面もあります。
途中かなり音を薄くしているところが複数ありますが、そこらへんは正直退屈ですね。複雑なリズムシークエンスをポリリズム的に重ねるのは面白いですが、それをもっとうまく発展させてほしかったです。録音だとわかりにくいですが、実はオーケストラの中にもピアノがあって、ソロのピアノとの組み合わせ方が面白い部分もありました。やはりこういう発見をするためには現地で聴かないといけないんですよねー。4.5。
4. Claire-Mélanie Sinnhuber (1973-): «Toccata» (2019) ※世界初演
-1h 19mn 30s-
ピアノソロでラジオフランスからの委嘱作品。ストラスブール生まれの女性作曲家。高等音楽院の後にIRCAMで学ぶ。
ピアノ演奏は2曲目と同じ彼女。一定リズムの無窮動で右手で高音部を弾きながら左手でピアノを叩いたり、足でピアノのペダル上部をゴンと蹴ったりする。こういうスタイルの曲自体は好きなんですが、これについてはあまり面白くなかったですね。ピアニズム面でも構成面でも目を引くところはありませんでした。3.0。
5. George Benjamin: «Palimpsests» (2002)
-1h 35mn 45s-
最後もベンジャミンのオーケストラ作品、ですが弦楽器の人数が少なくて、木管や金管と同じくらいの人数しかいません。怪しげなクラリネット群から始まり、金管が静寂を打ち破る。音響的には2曲目とは違って複雑に混ざった感じです。ハープ2台で面白い音を作ってるのが目立ちますね。
弦楽器の各パートがソロであることを活かした音作りは確かに面白いですし、劇版的ではない、ちゃんと音楽的に充実している作品だとは思いますが、やはりこれも2曲目同様、あまり構成的に面白いとは思えなかったです。もちろん僕の聴き方が甘いせいだという可能性は大いにありますが、時間経過の中での仕掛けというのをほとんど感じることが出来ないので、興味が最後まで持続しないです。4.0。
以上で1日目終了です。今週末と来週末が去年と同様複数コンサートをハシゴするので大変ですが頑張ります。
次はこちら。