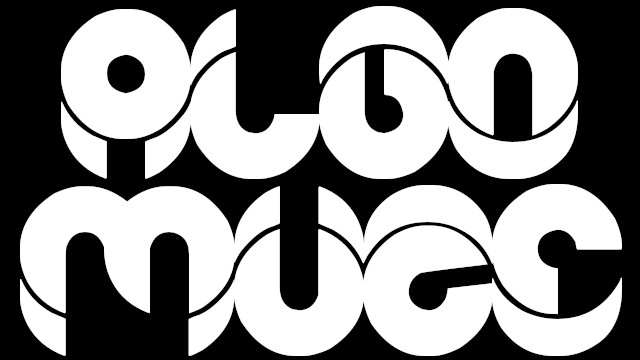6月末に音楽院の卒論の口頭試問がありました。これは提出した論文について15分のスピーチを行なった後で、論文の内容についての質問を審査官から受けるというものです。当然フランス語で喋らなければならないので、そのための台本を作ってから臨みました。この記事ではそれを公開します。論文そのものはこちら。

状況としては、口頭試問に作曲科の担当教員が一名いるのはわかっていたのですが、他の審査官は何が専門なのか、何人来るのかすらわかっていませんでした。で、提出した論文についてのスピーチが15分ぽっちで出来るはずもないので、最初からそれはやめておこうと思っていました。代わりに、論文の内容を補足するようなエピソードをいくつか語ろうと思って臨んだという次第です。
しゃべった内容は論文そのものに比べれば遥かにわかりやすいというか、普通のエピソードなので、あまり論文の内容にピンと来なかった人にも是非ご覧いただきたいです。
この記事では内容についての註釈を入れていこうと思っています。というのは、エピソードの細かい内容についてフランス語でいちいち説明するのは大変面倒だったので、簡略化したり、あるいは多少の捏造を混ぜながら実際はしゃべりました。なのでそういう箇所は※マークをつけて、青枠で註釈を入れていきます。
ではどうぞ。
◆ ◆ ◆
まず初めに、私の論文を読んで頂いたことを感謝します。これはとても長くて内容も複雑なので、きっと面倒な思いをさせたことだろうと思います。なので、もし時間をかけて私の論文を読んで頂いたのなら、それだけで私はとても満足です。
さて、今日は論文についての話をするつもりはありません。理由は単純に、15分では到底その内容を話すことができないからです。急いで書いたものですから修正したい箇所はたくさんあるのですが、それでも私が主張したいことはそこに全て書いてあります。この場でこれ以上付け加えることは何もありません。
なので今日は、私がなぜそのアイデアを思いついたのか、何に影響を受けてその考えに至ったのか、それについての二つの話をしようと思います。
まず一つ目の話は、私自身のことについてです。私は4歳の頃にバイオリンを習い始めたのですが、当初はそれほど音楽が好きではありませんでした。小学校に入ってからは野球チームに所属していた(※1)ので、そっちの活動の方がずっと楽しかったのです。14歳のときに野球チームを卒業してから(※2)少しずつ音楽に興味を持ち始めて、バイオリンも熱心に練習するようになりました。
※2 少年野球はもちろん小学校までで、中学に入ってからは学校の軟式野球部に所属していました。説明が面倒なので試験ではこういう話し方をしています。高校は野球の名門校だったのでそのつもりで進学したのですが、結局は野球を選ばずに音楽をやるようになったわけです。
そして16歳になった頃に、あるコンサートに行きました。バレンボイムが指揮する、ベルリン・シュターツカペレです(※)。私の故郷の札幌という街は人口200万人なので決して小さな都市ではありませんが、日本には東京や横浜や大阪といった大都市が他にありますから、有名な音楽家やオーケストラが日本に来ても、わざわざ札幌まで来てくれることは多くありません。事実、バレンボイムが札幌に来たのはその1回きりでした。幸運にも、私はそのたった1回のチャンスに巡り会うことができたのです。
プログラムの前半はベートーヴェンのピアノ協奏曲の弾き振りで、正直そちらの演奏は今はあまり覚えていません。ですがプログラム後半のマーラーの交響曲7番、こちらは今でもまだ鮮明に音を覚えているくらい、とても素晴らしい演奏でした。私が心から音楽に感動した、最初の体験でした。それがきっかけで、私は頻繁にコンサートへ行くようになりました。私は高校生の頃にハンバーガーショップでアルバイト(※)をしていたので数千ユーロの貯金があったのですが、その全てをコンサート代とCDを買うのに費やしました。ほぼ毎週のようにコンサートへ行き、毎日のようにCDを聴いていました。
そんな生活をしていたある日、急に音楽がわからなくなりました。確かに音は私の耳に入っているはずなのですが、一体音楽の何を聞いたらいいのかわからなくなってしまったのです。しかし演奏は止まってくれませんから、私は目の前を過ぎ去っていく音楽を前にただ佇むことしかできなくなってしまいました。100ユーロ払ってコンサートへ行っても何の収穫もなく終わる、そんなことが何度もありました。
そこで当時私のバイオリンの先生に相談してみました。
「先生、音楽がわからなくなってしまいました。音楽に集中できず、音が通り過ぎていってしまうのです」すると彼女はこう答えました。
「何も難しいことを考える必要はないのよ。ただ頭を空っぽにして、音楽に身を任せるだけでいいの」
私は「そうなんですね」と答えましたが、心の中では全然納得していませんでした。これは気持ち一つで解決できるような、そんな単純なことではないという確信があったからです。
その後も特に何かが解決するわけでもなく、よくわからないままコンサートへ行きCDを聴く日々が続いたのですが、2年ほど経ってからようやく一つの答えを得ることができました。それは何か。
日本には「木を見て森を見ず」という諺があります。これは物事の一部分に気を取られていると全体がわからなくなる、という意味です。多くの物事に通じる、良い諺だと思います。さて私が得た結論は何かと言うと、「木を見て、森も見る」ということです。音楽には流れの中で集中して聴くべきポイントがありますが、それと同時に全ての音も聴かなくてはいけないのです。
これは映画でもまったく同じことです。私たちは人物が喋っていればそこにしか目がいかないですし、まして字幕付きの作品だったらほとんどの人は字幕しか見ていません。しかしそれでは駄目なのです。喋っているときの人物の表情、体の動き、背景、レイアウトとカメラワークを目で見て、同時に声の演技、環境音、音楽を耳で聞く。これが「映画を見る」という行為なのです。しかもそれら全ての要素が等価値というわけではありません。見るべきポイント、聞くべきポイントが常に存在して、鑑賞者は集中力のバランスをそれに応じてその場その場で変えなくてはいけないのです。だから私は「木を見て、森も見る」という言い方をしたのです。
音楽の場合、それらの全てを耳だけでやらなければいけない、という風にも言えるわけです。これはとても難しいことです。このことに気づいて私はようやく納得しました。「音楽がわからない」というのは当然のことなのです。なぜなら音楽を聴くという行為そのものが非常に難しいものだからです。
これが私の作曲家としての哲学です。「音楽を聴くのは難しい。だからこそ、聴く人の集中力をどうやって生み出し、それを持続させるかという手段を、作曲家は第一に考えなければならない」これがAlgomuzeの一番重要な根本思想です。一つ目のエピソードは以上です。
二つ目は、「囲碁」の文化についてです。
ヨーロッパでは頭脳ゲームの王様はチェスですが、アジアの国々、特に中国、韓国、台湾、そして日本での王様は囲碁です(※)。これから私は囲碁の話をしますが、大部分はチェスと共通することなので、もしチェスに馴染みがあればそれと置き換えて私の話を聞いてください。
私は囲碁が人類の歴史上で最高の文化の一つであると考えています。その理由をお話しします。
日本の場合、「タイトル戦」と呼ばれる大きな大会が7つあり、プロ棋士の1年間の対局スケジュールはそれを中心にして決められています。ゴルフやテニスで言うところの4大大会、メジャー選手権のようなものです。タイトル戦に出場する棋士は当然、プロの中でもトップレベルの人だけです。だから、その対局は全てのプロ棋士が必ず見ます。リアルタイムで見れなくても、翌日までにはその棋譜を必ずチェックします。これをやらないプロ棋士は一人もいません。なぜなら、最先端の研究の成果がその対局に現れるからです。タイトル戦は日本の様々な地方都市で行われるのですが、スケジュールが空いている棋士はわざわざ現地まで行って、そこに集まった棋士同士でリアルタイムで対局内容の検討を行うのです(※)。
「最先端の研究を全てのプロ棋士がリアルタイムで検討する」、これがどれほど高度な文化であるかわかりますか。学問の世界ですら、ここまで透明な文化にはなれません。フェルマーの最終定理を証明したアンドリュー・ワイルズは、その過程で大きな困難がいくつもありました。その理由は、「定理を証明した」という栄誉はたった一人にしか与えられないからです。そのために、彼は自身の研究内容を発表のその日まで、ごく一部の人を除いて完全に隠す必要があり、したがって数々の問題を彼一人で解決しなければならなかったのです(※1)。この例以外にも、学問の世界では最新の研究内容を隠さなければいけない状況がいくつもあります(※2)。その点囲碁では、研究を隠しておく理由は何もありません。最新の研究は全て公開され、それを基にすぐさま次の研究が始まるのです。
※2 もちろん透明度の非常に高い学問分野もあるでしょう。しかしそれは学問一般に対して言えることではないということを言いたかったのです。特に国からの研究予算が多くついている場合や、企業研究の場合など。
学問が人類にとって最も価値ある営為であることは間違いありませんが、囲碁という文化はある意味ではそれすらも上回る側面があると私は思っています。この透明な文化への憧れ、これもまたAlgomuzeの思想の一つです。
もう一つ囲碁にまつわる面白い話をします。囲碁の対局時間は大会によって異なるのですが、場合によっては12時間以上行われることもあります(※1)。棋士は昼食や夕食を食べますが、それ以外は常に盤面の前で座っているだけです。にもかかわらず、対局が終わったあとには棋士の体重が1キロ、2キロ落ちるのです。なぜだかわかりますか。それほどまでに脳みそがエネルギーを消費するからです。囲碁の世界では「脳みそが汗をかく」(※2)という表現もあるくらい、人間の集中力の限界を試されるのです。この極限の集中こそが、私の理想とする人間の境地なのです。
※2 この表現はもはや一般的になったと思いますが、僕個人が最初に聞いたのは多分将棋棋士の誰かが言った言葉だったと記憶しています。
芸術家や音楽家が「宇宙の真理」や「神の声」を求めてLSDなどの薬物に手を出すことは珍しくありません。私は創造性を求めて薬物に手を出すことは決してないでしょう。それは倫理的な問題ではなく、薬物によって得られる創造性には限界があると考えているからです。もし本当に神の声を聞きたいと願うのなら、数学者や囲碁棋士のように訓練に訓練を重ねて極限の集中力を身につける以外の道はないと私は確信しています。
私はそれを音楽でも実現できるのではないかと考えています。それは先ほども述べた通り、音楽を聴くという行為は高い次元の集中力を要求するからです。最初は子供でも理解できる簡単な段階から始まり、少しずつ複雑になっていき、最終的には想像を絶する複雑性に至る。この道のりを、一つの作品の中で、あるいは複数の作品群の中で実現できないだろうか、という発想がAlgomuzeのアイデアの第一歩でした。
最後に、私はここまで囲碁は理想的な文化であると語ってきたわけですが、そんな囲碁の世界にも数年前に大変革が起きてしまいました。それが人工知能の登場です。2016年に、Google傘下のある企業が開発した人工知能プログラムが当時の韓国のトッププロ棋士を破って以降、人間はもう囲碁というゲームではコンピューターに勝てなくなってしまいました。そしてプロの研究に人工知能は必要不可欠なものになりました。これが意味するのは、「人間同士だけで行う研究の価値が著しく落ちた」ということです。先ほどお話ししたように、今でもなおプロ同士が集まって重要な対局の検討をすることはあるのですが、その際には必ず人工知能の示す見解を参照するわけです。人工知能を用いない研究は「不完全なもの」と見做されるようになったのです(※)。
囲碁のみならず全ての頭脳ゲームの最終的な目的は「ゲームそのものの解明」ですから、人工知能の登場によって研究が加速すること自体は歓迎すべきことです。しかし、私個人の見解では、「集団文化」としての囲碁の魅力は、かつての時代より失われてしまったなと思っています。こういった背景がありますので、私の論文の中でも人工知能の話題を取り扱った次第なのです。
私の発表は以上です。ご静聴ありがとうございました。
◆ ◆ ◆
以上が口頭試問のスピーチでした。時間は計っていませんがまあ多分15分から20分くらいに収まっているでしょう。最後の「集団文化としての囲碁の魅力」というのは結構難しいテーマなので、また別の機会に改めて書きたいなと思っています。
まあしかし、これを話しているときの審査官たちの表情というのが、なんかあんまりピンときてないような、さほど興味を惹かれてなさそうな雰囲気だったんですが、それが残念でしたね。僕のフランス語そのものの問題だったという可能性はさておいて、自分としては結構面白い話ができてると思ってたんですけどね、ご覧頂いた皆さんはどうでしょうかね。まあよければ感想でもください。